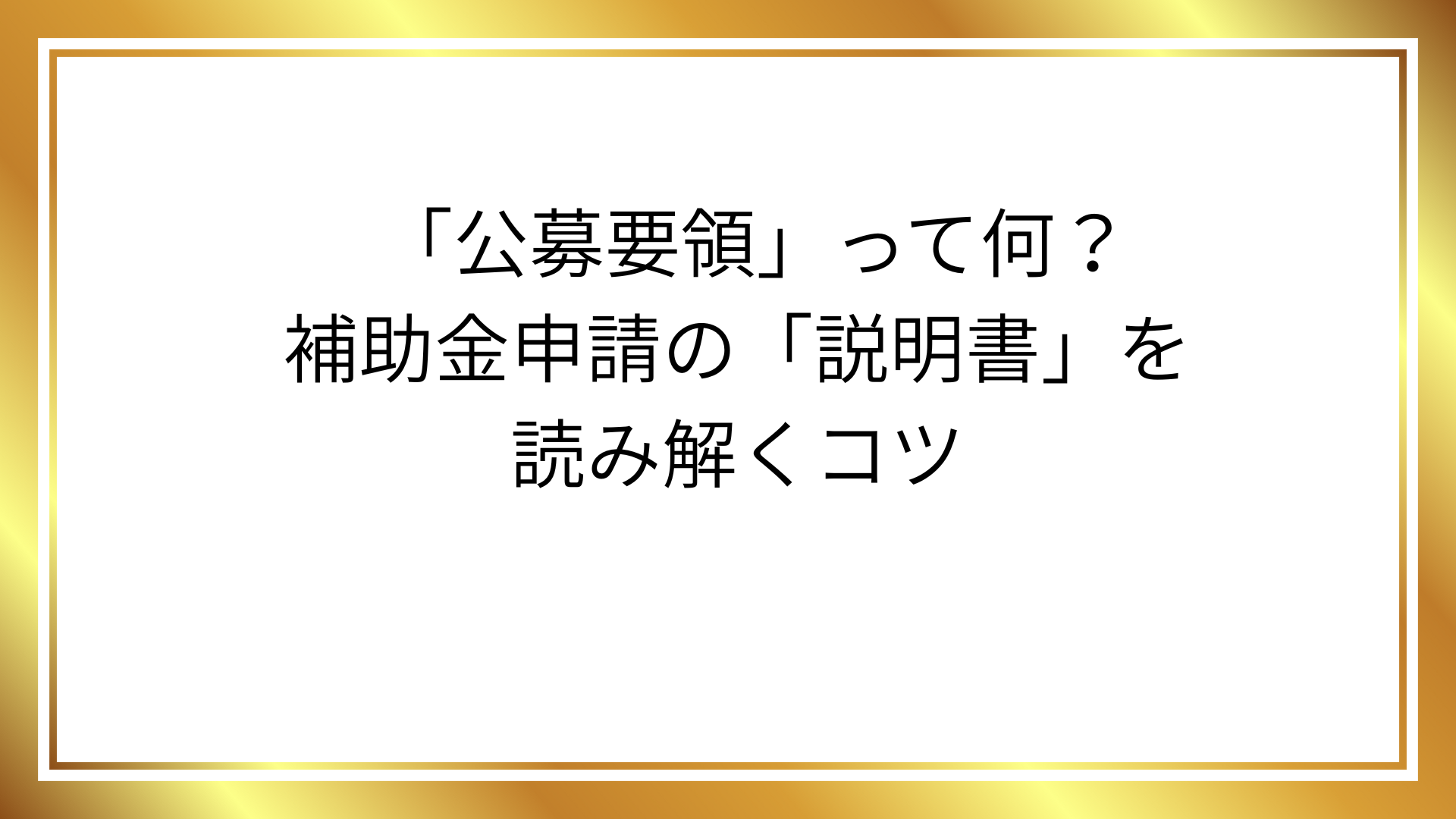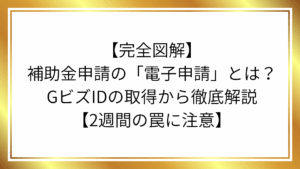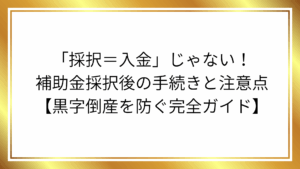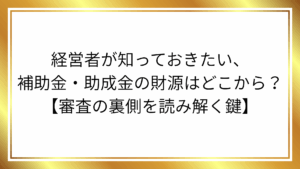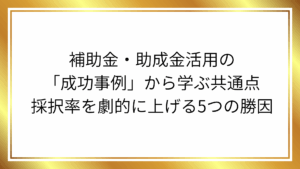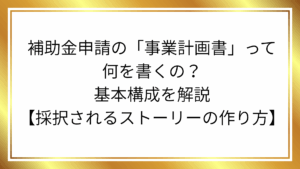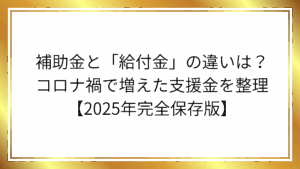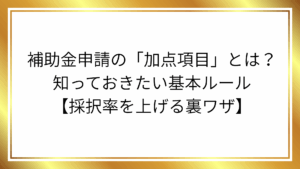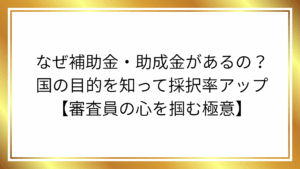「補助金に応募しよう!」
そう思い立って、公式サイトからダウンロードしたPDFファイル。
ファイル名は「公募要領(こうぼようりょう)」。
開いた瞬間、あなたの目に飛び込んでくるのは、
「30ページ、50ページ、時には100ページにも及ぶ、文字だらけの文章」
「見たこともないような難解な専門用語」
「複雑な表や、細かい注釈の嵐…」
正直、読む気が失せますよね。
「うわっ、面倒くさそう…」
「これ、全部読まないとダメなの?」
「専門家に丸投げしたくなってきた…」
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
日々、現場で忙しく働く経営者様にとって、この「お役所言葉の塊」と格闘する時間は、苦痛以外の何物でもないでしょう。
しかし、これだけは断言させてください。
補助金に採択される人(勝つ人)は、例外なく、この「公募要領」を”攻略”しています。
逆に、不採択になる人(負ける人)の9割は、公募要領を「なんとなく」しか読んでいません。
公募要領は、単なる「説明書」ではありません。
そこには、
「どんな会社を合格させるか」
「計画書に何を書けば点数がもらえるか(=答え)」
が、すべて書いてあるのです。
つまり、公募要領を読み解くことは、「テストの前に、カンニングペーパーを見る」のと同じくらい、強力なアドバンテージになるのです。
この記事は、公募要領アレルギーを持つあなたへ向けた、「日本一わかりやすい公募要領の読み解きガイド」です。
専門用語を翻訳し、読むべきポイントを絞り込み、難解なPDFを「宝の地図」に変えるテクニックを、余すところなく伝授します。
この記事を読めば、あの分厚いPDFが、あなたの味方に見えてくるはずです。
第1章:「公募要領」とは?なぜこれを読まないと100%落ちるのか
まずは、敵(?)の正体を知りましょう。
公募要領(こうぼようりょう)=「絶対的なルールブック」
公募要領とは、その補助金における「法律」そのものです。
国(事務局)は、ここに書かれているルールに基づいて、機械的に、厳格に審査を行います。
- 「対象者は、従業員20名以下の企業とする」→ 21名なら、どれだけ優れた企業でも不合格。
- 「郵送での申請は不可とする」→ 郵送した時点で、開封されずにゴミ箱行き。
- 「文字サイズは10.5ポイント以上とする」→ 小さい文字でびっしり書いても、読んでもらえない。
審査員は、あなたの会社の事情を汲んでくれません。
彼らが見ているのは「公募要領というモノサシに、合っているか、合っていないか」だけです。
だからこそ、ここを読み飛ばすことは、「ルールを知らずにスポーツの試合に出る」ようなものであり、100%負ける(不採択になる)のです。
補助金は「国からのラブレター(注文書)」である
視点を変えてみましょう。
なぜ、国はこんな面倒な書類を作るのでしょうか?
それは、国があなたに「こういう事業をしてほしい!」と注文しているからです。
- 「IT化を進めてほしい」
- 「賃上げをしてほしい」
- 「新しい輸出ビジネスに挑戦してほしい」
公募要領には、この「国の要望(=注文内容)」が事細かに書かれています。
採択されるコツはシンプルです。
「あなたの注文通り(公募要領通り)の計画を作りましたよ!」
とアピールすること。これに尽きます。
第2章:全部読むな!忙しい経営者のための「3点読み」テクニック
「重要性は分かった。でも、50ページも読む時間はない!」
ご安心ください。
公募要領は、1ページ目から順番に読む必要はありません。
実は、関係のない「事務的な記述」や「定型文」も大量に含まれています。
あなたが読むべきは、全体の「約2割」だけです。
では、どこを読めばいいのか?
絶対に外してはいけない「3つの急所(ポイント)」を教えます。
- 補助対象者(誰が?)
- 補助対象経費(何を?)
- 審査項目(どうすれば合格?)
まずは、この3点だけを「拾い読み」してください。
それだけで、勝率は劇的に変わります。
第3章:急所①「補助対象者」~そもそも、参加資格はあるか?~
PDFを開いたら、目次を見て「補助対象者」のページに飛びます。
ここで確認するのは、「足切りライン」です。
ここをチェック!「あなたは対象か?」
- 企業規模の定義:「中小企業」や「小規模事業者」の定義は、補助金によって微妙に違います。
- 資本金はいくらか?
- 従業員数は何人までか?
- 「みなし大企業(親会社が大企業)」は対象外か?
- 対象外となる業種:「医療法人」「社会福祉法人」「NPO法人」などは、対象外となる補助金が多いです。また、「風俗営業」などは原則NGです。
- 地域の限定:国の補助金なら全国対象ですが、自治体の補助金なら「市内に本社があること」などが条件になります。
【翻訳】
ここを読んで「あ、ウチは対象外だ」と分かれば、その瞬間に読むのをやめてOKです。時間の無駄を防げます。
第4章:急所②「補助対象経費」~買いたいモノは対象か?~
次に、「補助対象経費」のページを探します。
経営者様が一番知りたい「このパソコン代は出るのか?」の答えは、ここにあります。
ここをチェック!「その買い物、経費で落ちる?」
多くの公募要領には、「対象経費の区分」という表があります。
- 【◯ 対象になるもの】
- 機械装置費、システム構築費
- 広報費(WEB制作、チラシ)
- 専門家謝金
- 【× 対象にならないもの(対象外経費)】
- 汎用性があるもの(パソコン、タブレット、車)
- 不動産購入費
- 既存の人件費、家賃
特に注意!「注釈(※)」こそが重要
表の下に小さく書かれている「※(注釈)」や「(カッコ書き)」を見逃さないでください。ここに「罠」があります。
- (例)「WEB制作費は対象とする。ただし、単なる会社案内サイトの作成は対象外とし、EC機能や予約機能を持つものに限る」
- (例)「中古品の購入は、3社以上の相見積もりが必須である」
【コツ】
あなたが欲しいモノが、この「対象」に入っているか。そして「注釈」で禁止されていないか。これを指差し確認してください。
第5章:急所③「審査項目」~これが合格へのカンニングペーパーだ!~
ここが、この記事のハイライトです。
多くの人が読み飛ばしますが、ここを読むか読まないかで、採択率が天と地ほど変わります。
公募要領の後半に、必ず「審査の観点」や「審査項目」というページがあります。
これ、何だと思いますか?
これは、国がこっそり教えてくれている「採点の答え(配点基準)」なのです。
審査員は、ここを見て点数をつけている
審査員の手元には、「採点シート」があります。そのシートには、この「審査項目」がそのまま書かれています。
- (例)ものづくり補助金の審査項目より(※イメージ)
- ① 革新性:自社だけでなく、他社と差別化された新しい取り組みか?
- ② 事業化の可能性:市場ニーズがあり、売上が立つ根拠があるか?
- ③ 費用対効果:投資した金額に見合う利益が出るか?
【実践】「審査項目」を事業計画書に反映させる方法
もし、審査項目に「地域経済への波及効果」と書いてあったら、どうしますか?
- ダメな人:自分の事業の売上のことしか書かない。→ 審査員「地域への貢献については書いてないな。0点」
- デキる人:計画書の中に「本事業による地域への貢献」という見出しを作り、「地元の食材を使うことで、地域農家へ〇〇円の利益をもたらします」と書く。→ 審査員「お、書いてあるね。加点!」
【結論】
事業計画書を書くときは、「審査項目」を横に置き、書かれているキーワードをすべて盛り込んでください。
それだけで、あなたの計画書は「模範解答」になります。
第6章:「お役所用語」翻訳辞典 ~ これが出たら要注意! ~
公募要領を難解にしている元凶、「独特な用語」。
これらを「普通の日本語」に翻訳します。これを知っておくだけで、読むスピードが倍になります。
①「原則として~」(げんそくとして)
- お役所語: 「原則として、交付決定後の発注に限る」
- 翻訳: 「例外はほぼ認めないから、絶対に守れ」
- 解説: 「原則」と書いてあると「例外があるのかな?」と思いがちですが、補助金においては「99.9%、そのルール通りにやれ」という強い命令です。
②「~等(など)」
- お役所語: 「機械装置等費」
- 翻訳: 「その他にも含まれる可能性があるが、勝手に判断するな」
- 解説: 「等」に含まれるかどうかは、自己判断せず、必ず事務局に確認しましょう。
③「専ら(もっぱら)」
- お役所語: 「補助事業のために専ら使用するもの」
- 翻訳: 「その事業”だけ”に使うもの(他の仕事やプライベートで1ミリも使うな)」
- 解説: これがある場合、パソコンや車などは「プライベートでも使えるじゃん」と言われて即NGになります。
④「相見積もり(あいみつもり)」
- お役所語: 「発注に際しては、相見積もりを取得すること」
- 翻訳: 「1社だけで決めるな。2~3社の見積もりを取って、一番安いところにしろ」
- 解説: これを忘れて発注すると、対象外になります。
⑤「遡及適用(そきゅうてきよう)」
- お役所語: 「遡及適用は認めない」
- 翻訳: 「過去にさかのぼってOKにはしない(フライングは許さない)」
- 解説: 「申請前に買っちゃったけど、後から補助金ちょうだい」は通用しません。
第7章:見逃し厳禁!「スケジュール」と「提出方法」
中身が理解できても、提出ルールを間違えたら終わりです。
公募要領の最初か最後に書かれている、ここだけはマーカーを引いてください。
1. 締切日時は「17:00」厳守!
「〇月〇日(金)17:00 必着」
これ、本当に「17:00:00」でシステムが止まります。
17:00:01 に送信ボタンを押しても、エラーで弾かれます。
「サーバーが混んでて…」という言い訳は一切通用しません。
「締切は前日」だと思って動いてください。
2. 申請方法は「電子申請(GビズID)」のみ?
最近は「郵送不可」「持ち込み不可」が当たり前です。
そして、電子申請には「GビズID(プライム)」が必須と書かれているはずです。
- 要注意:公募要領に「GビズIDが必要」と書いてあったら、今すぐID取得申請をしてください。ID発行に2週間かかります。「要領を読んだのが締切3日前」だったら、その時点でゲームオーバーです。
3. 必要な「添付書類」リスト
- 決算書(何期分?)
- 開業届
- 納税証明書(どの種類の?)
これらも、発行に時間がかかるものがあります。
公募要領には「提出書類チェックリスト」がついていることが多いので、印刷して一つずつチェックを入れましょう。
第8章:実践編!公募要領を「武器」にするための4ステップ
最後に、今日からできる具体的なアクションプランをまとめます。
ステップ1:公式サイトから「最新版」をダウンロードする
公募要領は、公募のたび(第1回、第2回…)に微妙に内容が変わります。
必ず「今回の公募回」の、「最新版(Ver.〇〇)」をダウンロードしてください。
古い要領で準備すると、ルール変更で泣きを見ることがあります。
ステップ2:印刷して、蛍光ペンを持つ
画面で見るより、紙に印刷することをお勧めします。
そして、以下の3色でマーカーを引きまくります。
- 赤: 「締切」「提出書類」「NG要件」(絶対に守るべきこと)
- 青: 「対象経費」(自分の欲しいものが含まれるか)
- 黄: 「審査項目」(事業計画書に書くべきキーワード)
ステップ3:分からないことは「事務局」に電話する
公募要領を読んでも、「ウチのこの経費は対象かな…?」と迷う「グレーゾーン」が必ず出てきます。
その時は、悩まずに「公募要領の最後」に書いてある「事務局コールセンター」に電話してください。
「公募要領の〇ページの〇〇について質問ですが…」
と言えば、彼らは丁寧に教えてくれます。
(※自己判断が一番危険です!)
ステップ4:専門家に依頼する場合も、自分でも読む
「難しそうだから、コンサルタントに頼もう」
それも賢い選択です。
しかし、あなた自身も一度は目を通してください。
あなたが公募要領(ルール)を知っていれば、
「先生、要領にはこう書いてありますが、この計画で大丈夫ですか?」
とチェックを入れることができます。
丸投げして、専門家がミスをして不採択になっても、誰も責任を取ってくれません。自分の身を守るためにも、一通り目を通すことは必須です。
まとめ:「公募要領」は、合格へのパスポート
「公募要領」という難解なPDF。
ここまで読んだあなたなら、もう以前のような「得体の知れない恐怖」は感じていないはずです。
それは、単なる「面倒な説明書」ではありません。
国があなたにこっそり渡してくれた、
「ここさえ押さえれば、あなたにお金をあげますよ」
という、合格へのパスポート(招待状)です。
- 「対象者」で足切りを回避し、
- 「対象経費」で欲しいモノを確認し、
- 「審査項目」をカンニングして計画書を書く。
このプロセスを踏めば、あなたの申請書のレベルは、ライバルたちより頭一つ、いや二つ抜け出します。
さあ、今すぐ、あなたが狙っている補助金の公式サイトを開き、「公募要領」をダウンロードしてみましょう。
そして、蛍光ペンを片手に、宝探しを始めてみてください。
その数時間の「読解」が、数ヶ月後に数百万円の「採択」という果実となって、あなたの元へ返ってくるはずです。