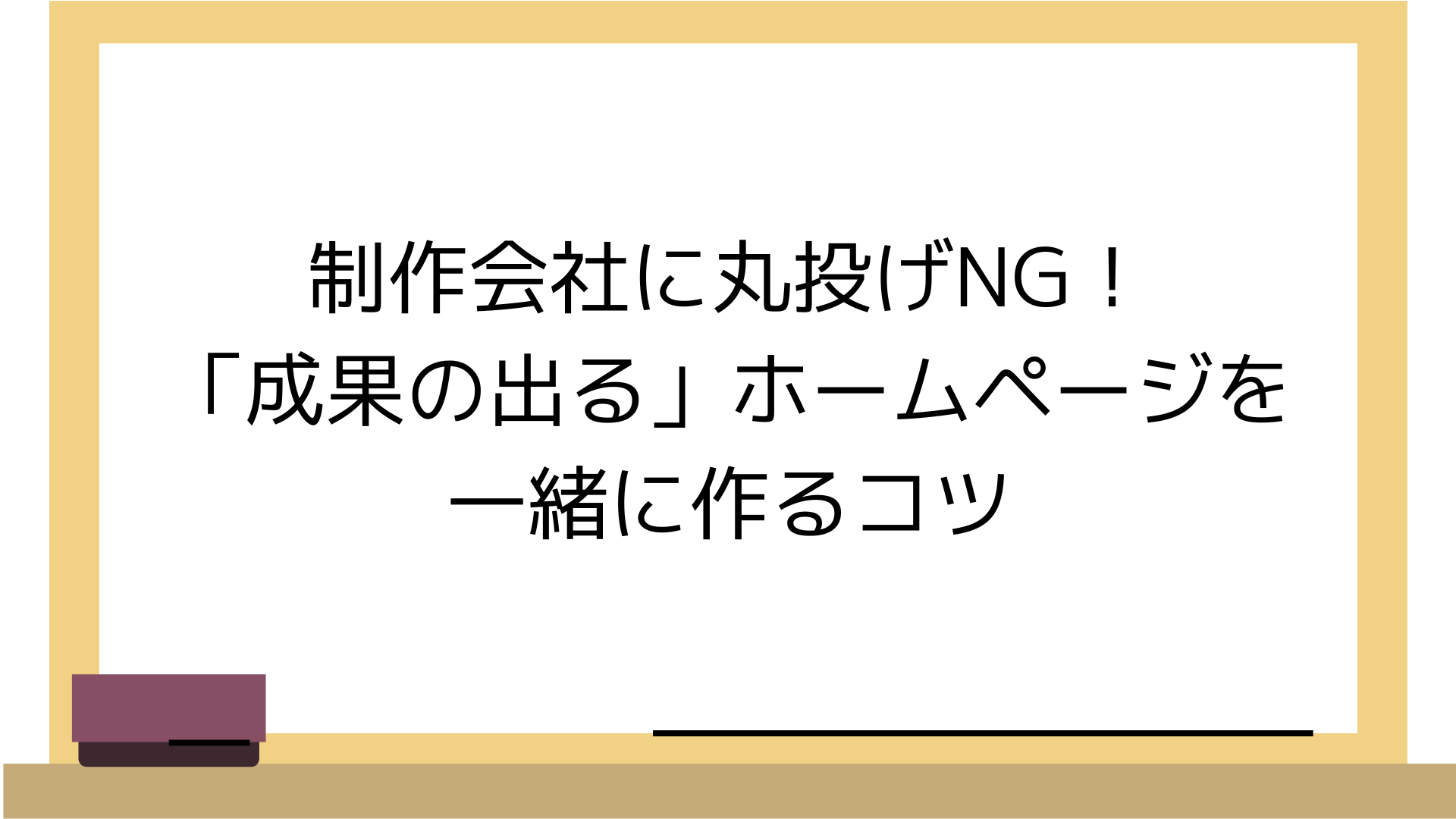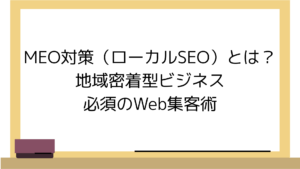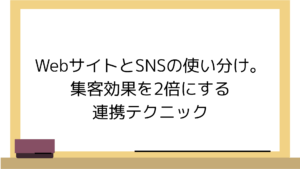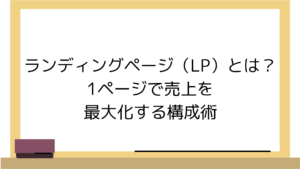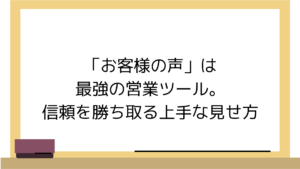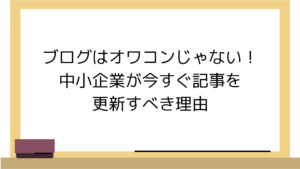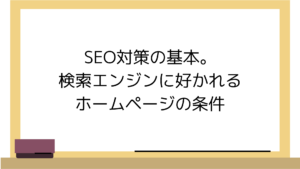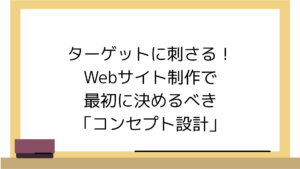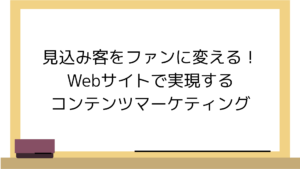「プロにお金を払うんだから、あとは全部お任せでいいだろう」
「自分はWebのことは分からないし、口を出さない方がいいものができるはずだ」
「忙しくて時間がないから、とりあえず『いい感じ』に作っておいてよ」
もし、貴社が今、ホームページ制作に対してこのようなスタンスをお持ちだとしたら、少しだけ立ち止まってください。
厳しいことを申し上げますが、「丸投げ」で作ったホームページが、ビジネスで成果を上げることは、100%ありません。
こんにちは。私はこれまで、数多くの企業のWeb戦略を支援してきましたが、失敗するプロジェクトには必ず共通点があります。それは、発注者である経営者が「思考停止(丸投げ)」してしまっていることです。
逆に、爆発的な集客を生み出すホームページには、必ず「経営者の魂」が入っています。
制作会社は「Web構築のプロ」ですが、「貴社のビジネスのプロ」ではありません。
貴社の強み、顧客の悩み、業界の商習慣を一番知っているのは、間違いなく貴社自身です。
この記事では、なぜ丸投げが失敗するのかという根本的な理由から、制作会社を「下請け」ではなく「最強のパートナー」に変え、成果の出るホームページを「一緒に作り上げる」ための具体的な5つのコツを徹底解説します。
これは、制作費をドブに捨てず、貴社のビジネスを加速させるための「発注者としての流儀」のお話です。
1. なぜ「丸投げ」すると、綺麗なゴミができてしまうのか?
まず、なぜ「プロに任せる」ことが「丸投げ」になってはいけないのか。その構造的な欠陥を理解しましょう。
制作会社は「貴社の強み」を知らない
制作会社のデザイナーやディレクターは、Webサイトを作る技術は一流です。しかし、貴社の業界のことや、貴社がどんな思いで創業し、どんなこだわりを持って商品を作っているかについては「素人」です。
丸投げするということは、「中身のない箱」を作ってもらうようなものです。
結果として出来上がるのは、「デザインは綺麗だけど、どこにでもあるありきたりな文章が並んだ、誰の心にも響かないサイト」です。これを業界では「綺麗なゴミ」と呼ぶことさえあります。
「いい感じ」の定義がズレている
「かっこよくしてください」「いい感じにしてください」
これは、制作現場で最も困るオーダーです。
- 経営者の思う「いい感じ」:重厚感があって、伝統を感じさせるデザイン
- 制作会社の思う「いい感じ」:今風の、スタイリッシュで余白の多いデザイン
この認識のズレ(コミュニケーションロス)を埋めないまま進めると、納品直前になって「思っていたのと違う!」というトラブルが発生します。
これを防ぐには、貴社の頭の中にあるイメージを、言葉や参考サイトで具体的に伝える「翻訳作業」が不可欠です。
目的が「作ること」になってしまう
丸投げされた制作会社は、どう考えるでしょうか?
「お客様からの指示がないから、無難に作って、納期通りに納品することを最優先しよう」と考えます。
本来の目的は「集客すること」や「売上を上げること」だったはずなのに、いつの間にか「ホームページを完成させること」がゴールになってしまいます。
これでは、魂の入った「売れるサイト」になるはずがありません。
2. 成果を出すための「役割分担」を理解する
成功するプロジェクトでは、発注者(貴社)と受注者(制作会社)の役割が明確です。二社は「上下関係」ではなく、ゴールを共有する「対等なパートナー」であるべきです。
経営者(貴社)の役割:戦略と情熱
Webの知識はなくて構いません。貴社が担うべきは、以下の「ビジネスの根幹」部分です。
- 誰に売りたいか(ターゲット)
- 何を売るか(商品・サービス)
- なぜ貴社なのか(競合優位性・USP)
- このビジネスにかける想い(理念)
これらは、制作会社には絶対に作れません。貴社の中からひねり出すしかない「原液」です。
制作会社の役割:翻訳と増幅
制作会社の役割は、貴社から出てきた「原液」を、Webという世界で最も伝わりやすい形に「翻訳」し、デザインの力で魅力を「増幅」させることです。
- 情報の整理(サイト構成)
- 視覚的な表現(デザイン)
- 検索エンジン対策(SEO)
- 使いやすさの追求(UI/UX)
「貴社の情熱 × 制作会社の技術 = 成果」
この掛け算を成立させるためには、両者が汗をかく必要があります。
3. 制作会社と一緒に汗をかく!「成果が出る」5つのコツ
それでは、具体的にどうやって制作会社と協力すればよいのか。明日から使える実践的な5つのコツを伝授します。
コツ1:RFP(提案依頼書)まではいかなくても「要望シート」は自作する
制作会社に会う前に、A4用紙1枚でいいので、以下の項目を書き出してください。
- Webサイトを作る目的(例:電話問い合わせを月10件増やしたい)
- ターゲット顧客(例:40代の建設会社社長、スマホで検索する)
- 自社の強み(例:他社より納期が半分、社長が現場に出る)
- 参考サイト(例:デザインは〇〇社のサイトが好き、雰囲気は△△に近い)
- 予算と納期
これを渡すだけで、制作会社は「このお客様は本気だ」「方向性が明確で提案しやすい」と感じ、提案の質が劇的に上がります。
コツ2:写真と原稿には「自前」を混ぜる
「写真も文章もお任せで」と言うと、制作会社は「素材サイト」にある、外国人が握手している写真や、当たり障りのないフリー素材を使います。これでは信頼感が出ません。
- 写真:スマホで撮ったものでも構いません。社長の顔、スタッフの笑顔、オフィスの様子、作業風景など、「リアルな空気感」が伝わる写真を提供してください。
- 原稿:キャッチコピーはプロに任せても良いですが、「代表挨拶」や「商品へのこだわり」の箇条書きは、貴社自身の言葉で書いてください。不器用な言葉でも、熱量が違います。
コツ3:「好き嫌い」ではなく「顧客目線」でフィードバックする
デザイン案が出てきた時、修正指示を出す場面でやってはいけないのが、「なんとなく赤が好きだから赤にして」という主観的な指示です。
Webサイトを見るのは、貴社ではなく「お客様」です。
「ターゲットは40代の男性経営者だから、もっと落ち着いた青色の方が信頼されるのではないか?」
このように、常に「ターゲットにとってどうか?」という視点で議論を投げかけてください。そうすれば、制作会社もプロとして的確なアドバイスを返してくれます。
コツ4:分からないことは「素直に聞く」
Web用語は難解です。「SEO」「レスポンシブ」「CVR」…。
知ったかぶりをして「あ、それでいいです」と流してしまうのが一番危険です。
「素人で申し訳ないけど、今の言葉はどういう意味ですか? ビジネスにどう影響しますか?」
と、恥ずかしがらずに聞いてください。
良い制作会社なら、小学生でも分かる言葉で説明してくれます。逆に、専門用語で煙に巻こうとする会社は、その時点でパートナー失格です。
コツ5:公開後の「運用」を前提に話す
ホームページは作って終わりではありません。
「公開した後、ブログはどう更新すればいい?」「アクセス解析はどう見るの?」
制作段階から、公開後の運用について質問し、相談してください。
「作ったら終わりですよ」というスタンスの会社ではなく、「公開後も一緒に育てていきましょう」と言ってくれる会社を見極めるリトマス試験紙にもなります。
4. 良い制作会社を見抜く「魔法の質問」
これから制作会社を選ぶ貴社に、相手が「パートナーとしてふさわしいか」を見抜くための質問を一つ授けます。
「御社がこれまでに作ったサイトで、一番成果が出た事例と、なぜ成果が出たのかを教えてください」
- ダメな回答:「このサイトはデザイン賞を取りました」「最新のアニメーションを使いました」→ デザイン(手段)の話しかしていない。
- 良い回答:「この工務店様は、強みを『地域密着』に絞り込み、お客様の声を前面に出したことで、問い合わせが倍増しました」→ クライアントのビジネス(目的)を理解し、戦略の話をしている。
貴社のビジネスに興味を持ち、「なぜ?」を深掘りしてくれる会社こそが、選ぶべきパートナーです。
5. まとめ:貴社の「本気」が制作会社を動かす
「丸投げNG」と言うと、面倒に感じるかもしれません。
しかし、数ヶ月間、制作会社と膝を突き合わせて議論し、自社の強みを再確認するプロセスは、Webサイト制作を超えて、貴社の経営そのものをブラッシュアップする貴重な機会になります。
貴社が本気で向き合えば、制作会社もプロとしてのプライドをかけて、本気で応えてくれます。
その熱量のぶつかり合いからしか、「人の心を動かすWebサイト」は生まれません。
どうか、制作会社を「下請け」と思わず、「共同プロジェクトの仲間」として迎え入れてください。
「一緒にいいものを作ろう」という貴社の姿勢が、最高の結果を生む最初の一歩です。
貴社のビジネスの魂が宿った、成果の出るホームページが完成することを、心より応援しております。