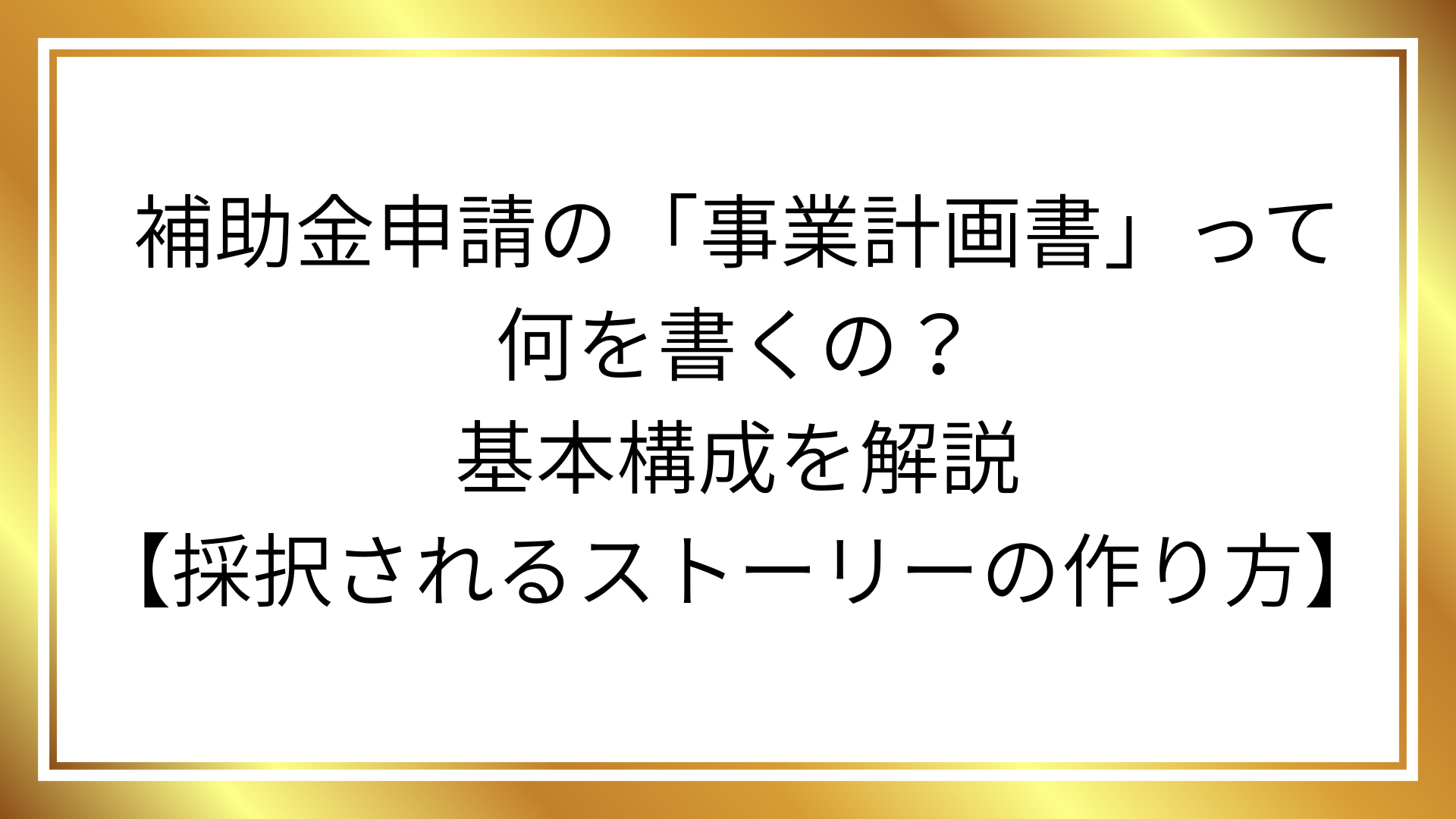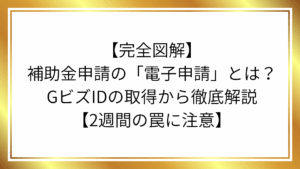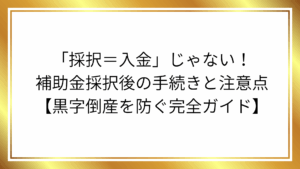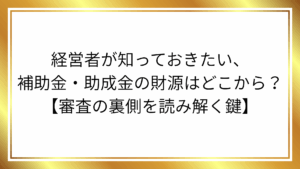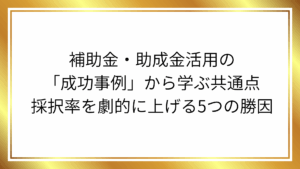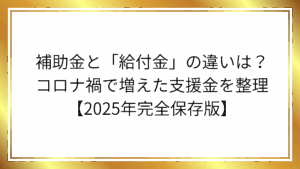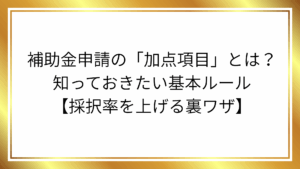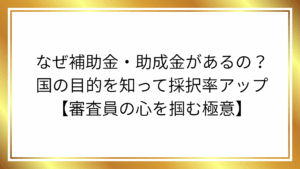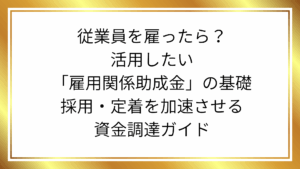「補助金を申請したいけれど、事業計画書なんて書いたことがない…」
「作文は苦手だし、どんな構成にすれば審査員に響くのか見当もつかない」
「難しそうだから、やっぱり諦めようかな…」
補助金という言葉に魅力を感じながらも、この「事業計画書(じぎょうけいかくしょ)」という高い壁の前に立ち尽くし、申請を断念してしまう経営者様が後を絶ちません。
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
日々の業務で手一杯の中、慣れないデスクワークで、しかも「国の審査」に通る書類を作れと言われても、途方に暮れてしまうのは当然です。
しかし、断言させてください。
事業計画書は、「文才」や「文学的な表現」は一切不要です。
必要なのは、「正しい型(テンプレート)」と「論理的なストーリー」だけです。
審査員は、あなたの文章力を採点しているわけではありません。
「この会社にお金を渡せば、本当に成長するのか?」
この一点だけを見ています。
この記事は、補助金申請の初心者である個人事業主・中小企業経営者様に向けた、「世界一わかりやすい事業計画書の書き方バイブル」です。
審査員が思わず「合格!」のハンコを押したくなる「黄金の4部構成」と、各項目に書くべき「具体的なネタ」を、ゼロから徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、白紙だったパソコンの画面に向かうのが、少し楽しみになっているはずです。
さあ、御社の未来を切り拓く「最強の設計図」を、一緒に作り上げていきましょう。
第1章:マインドセットを変えよう!事業計画書は「ラブレター」である
書き方のテクニックに入る前に、一つだけ重要な「意識改革」をお願いします。
多くの経営者様が、事業計画書を「国にお金を恵んでもらうための”お願い文書”」だと思っています。
これが、不採択になる最大の原因です。
補助金は「救済」ではなく「投資」です。
国(審査員)は、税金を預かる投資家です。
つまり、事業計画書とは、
「私(御社)に投資してくれれば、こんなに素晴らしい成果(リターン)を出して見せますよ!」
と、相手を口説き落とすための「ラブレター(プレゼン資料)」なのです。
審査員が知りたいのは「3つのこと」だけ
審査員は、何百枚もの書類を読みます。彼らが探している答えは、実はシンプルに3つだけです。
- Why You?(なぜ、あなたなのか?)
- 御社には、それを実現できる「強み」や「実績」がありますか?
- Why Now?(なぜ、今なのか?)
- なぜ今、その投資が必要なのですか? 市場のチャンスはありますか?
- How?(どうやって?)
- その計画は、絵空事ではなく、現実的に実行可能ですか?
この3つの問いに、明確に答えてあげること。
それが、事業計画書のすべてです。
第2章:これだけ書けばOK!「黄金の4部構成」テンプレート
補助金の種類(小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金など)によって、細かい様式は異なります。
しかし、合格する計画書の「骨組み」は、驚くほど共通しています。
以下の「黄金の4部構成」を頭に入れてください。
この順番通りに書けば、論理的で説得力のあるストーリーが自動的に完成します。
- 【現状分析】 私たちはこんな会社で、こんな強みを持っています。
- 【課題と機会】 でも今、こんなチャンス(またはピンチ)があり、ここが課題です。
- 【解決策(補助事業)】 そこで、補助金を使って「これ」を導入し、課題を解決します。
- 【効果】 その結果、こんなに売上が上がり、会社が成長します。
まるで「起承転結」のドラマのように、ストーリーを繋いでいくのです。
では、各パートに具体的に何を書けばいいのか、詳しく見ていきましょう。
第3章:【パート1】現状分析 ~「自社の強み」を自慢しよう~
最初のパートは、自己紹介です。
しかし、ただ「〇〇市で飲食店をやっています」だけでは弱すぎます。
ここでは、「ウチの会社は、投資する価値がある良い会社ですよ」とアピールする必要があります。
書くべき3つの要素
- 基本情報(誰が、どこで、何を)
- 創業年数、業種、従業員数、主な商品・サービス。
- 経営理念(どのような想いでやっているか)。
- 顧客ターゲット(誰に)
- メインのお客様はどんな人か?(例:近隣に住む30〜40代の子育て世帯)
- どんなニーズを持って来店しているか?
- 自社の強み(SWOT分析の”S”)
- ここが最重要です。 競合他社にはない、御社だけの「武器」は何ですか?
- 「味が美味しい」「親切丁寧」といった抽象的な言葉はNGです。
- (良い例):
- 「創業50年の歴史があり、親子3代で通う固定客が300名いる(顧客基盤)」
- 「店主は〇〇コンテストで入賞歴があり、他店にはない技術がある(技術力)」
- 「駅から徒歩1分の好立地で、雨の日でも集客が落ちない(立地)」
「強みなんてないよ…」とおっしゃる経営者様もいますが、必ずあります。
「長く続いている」こと自体が信用ですし、「常連さんがいる」ことも立派な強みです。客観的な数字や事実(〇〇年、〇〇人など)を入れて、具体的に自慢してください。
第4章:【パート2】課題と機会 ~「なぜ今やるのか」を語る~
現状の自慢が終わったら、次は「なぜ今回、新しい投資が必要なのか」という動機を説明します。
1. 市場の動向(市場のチャンス)
世の中や業界が、今どう動いているかを書きます。
- 「コロナ禍が明け、インバウンド需要が急増している」
- 「健康志向の高まりで、オーガニック食品の市場が年率〇%で伸びている」
- 「人手不足が深刻で、デジタル化による効率化が業界全体の課題だ」
2. 自社の課題(ボトルネック)
市場にチャンスはあるのに、今のままの御社ではそれを取り込めない「理由」を書きます。
- 「外国人客が増えているのに、英語メニューや決済端末がなく、機会損失している」
- 「手作りにこだわっているが、注文が増えすぎて生産が追いつかない」
- 「技術には自信があるが、Web発信をしていないため、新規客に知られていない」
「チャンスはある。でも、今の設備(体制)では限界がある」
このジレンマを明確にすることで、次の「解決策」が輝きます。
第5章:【パート3】解決策(補助事業) ~「何にお金を使うか」~
ここが補助金申請のメインディッシュです。
「補助金を使って何を買うか」、そして「それをどう活用するか」を書きます。
1. 導入するモノ(What)
- 「最新の自動調理機(〇〇社製)を導入する」
- 「多言語対応の券売機と、モバイルオーダーシステムを導入する」
- 「プロに依頼して、SEO対策済みのホームページを制作する」
2. 具体的な取り組み内容(How)
ただ「買います」ではダメです。「買って、どうするか」を書きます。
- 「自動調理機の導入により、仕込み時間を1日3時間短縮する」
- 「短縮した時間を使って、新メニュー〇〇を開発する」
- 「ホームページでブログを毎週更新し、SNS広告と連動させて集客を行う」
3. スケジュール(When)
いつ発注し、いつ納品され、いつから稼働するのか。
現実的なスケジュールを引いて、「計画性がある」ことをアピールします。
ここで重要なのは、「パート2の課題」と「パート3の解決策」が、パズルのようにピッタリ合っていることです。
「人手不足が課題」と言っているのに、「看板を新しくする」という解決策では、審査員は「?」となります。
「人手不足」→「だから、自動化マシンを入れる」という一本の筋を通してください。
第6章:【パート4】効果 ~「輝かしい未来」を数字で示す~
最後は、投資した結果、会社がどうなるかという「ハッピーエンド」を描きます。
ここでのポイントは、「定性面」と「定量面」の両方を書くことです。
1. 定性的な効果(どんな良いことがあるか)
- 「スタッフの残業が減り、職場の雰囲気が良くなる」
- 「お客様の待ち時間が減り、満足度が向上する」
- 「新しい層(若年層など)のお客様が増える」
2. 定量的な効果(数字でどうなるか)
審査員が最も重視するのがここです。投資に対するリターンを「数字」で約束します。
- 「売上が現在の年間2,000万円から、1年後には2,400万円(120%)にアップする」
- 「原価率が5%改善し、利益率が向上する」
- 「客単価が1,000円から1,200円に上がる」
「なぜその数字になるのか?」という根拠も添えてください。
(例:「1日あたり新規客が3人増え、営業日数が25日なので、月間〇〇円の増収見込み」など)
第7章:採択率を劇的に上げる「3つのスパイス」
基本構成は以上ですが、さらに採択率を高めるために、プロが入れている「スパイス(テクニック)」を3つ伝授します。
スパイス①:「写真」と「図解」を入れまくる
百聞は一見にしかず。文字だけの計画書は、審査員を疲れさせます。
- 「現在のお店の外観写真」
- 「導入したい機械のパンフレット画像」
- 「売上目標のグラフ」これらをふんだんに盛り込み、「パッと見て分かる」書類にしてください。これだけで評価は跳ね上がります。
スパイス②:「公募要領のキーワード」を散りばめる
公募要領(ルールブック)には、国の「やってほしいこと」が書いてあります。
(例:生産性向上、インボイス対応、賃上げ、販路開拓…)
これらの単語を、計画書の中に意図的に散りばめてください。
「この計画は、御国(みくに)の方針に合致していますよ」というアピールになります。
スパイス③:第三者の目を入れる
自分だけで書いていると、独りよがりになりがちです。
書き上げたら、家族や従業員、あるいは商工会議所の担当者などに見せて、
「これ読んで、意味わかる? ワクワクする?」
と聞いてみてください。
他人が読んで理解できない計画書は、審査員にも理解されません。
第8章:書けない時はどうする?「お助けツール」紹介
「構成は分かったけど、やっぱり文章を書くのは苦手だ…」
そんな時のための、強力な味方を紹介します。
1. 生成AI(ChatGPTなど)を活用する
今や、AIは最強の壁打ち相手です。
「私は〇〇県でカフェをやっています。強みは自家焙煎です。Web集客を強化するための補助金申請の事業計画書の『強み』と『課題』のたたき台を作って」
と指示すれば、驚くほど精度の高い文章案を出してくれます。
2. 商工会議所・商工会に相談する
地域の商工会議所には、補助金申請の指導員がいます。
書きかけの計画書を持っていけば、「ここはもっと具体的に」「ここは数字を入れて」と無料で添削してくれます。特に「小規模事業者持続化補助金」の場合は、商工会議所の確認印が必要になるケースも多いので、早めに相談に行きましょう。
3. 認定支援機関(専門家)に頼る
「ものづくり補助金」などの大型補助金や、どうしても時間がない場合は、行政書士や中小企業診断士などのプロ(認定支援機関)に報酬を払ってサポートを依頼するのも、賢い経営判断です。
まとめ:事業計画書は、会社の「未来地図」である
「事業計画書の書き方」について解説してきました。
- 現状分析(強み)
- 課題と機会
- 解決策(補助金活用)
- 効果(数値目標)
この4つのステップで、あなたの頭の中にある構想を文字にするだけです。
最後に、ひとつだけお伝えしたいことがあります。
苦労して書き上げた事業計画書は、単なる「申請書類」ではありません。
それは、御社の進むべき道を明確にし、迷った時に立ち返るべき「未来への航海図」そのものです。
「補助金をもらうため」だけでなく、
「自分の会社を、もっと良くするため」に。
この機会に、一度じっくりとパソコンに向き合い、御社の未来を描いてみませんか?
その時間は、補助金という金銭的価値以上に、経営者としてのあなたを大きく成長させてくれるはずです。
まずは、メモ書きで構いません。
「ウチの強みって何だろう?」と、箇条書きにすることから始めてみてください。